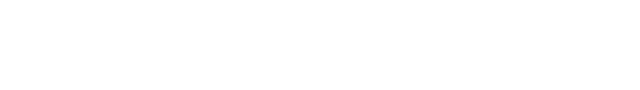タンパク尿とは?原因と改善のための治療方法
こんにちは、透析予防のクリニック、赤羽もりクリニックの院長の森 維久郎です。
今回は腎機能のSOSの役割を示す「タンパク尿」についての解説記事を書きます。
健康診断などで異常を指摘されるも、症状がないことや、医療関係者の中でもしっかり認知されておらず、放置されがちな検査異常です。
腎臓という臓器は一度悪くなると良くならないので、健康診断などで異常を指摘された患者様にはぜひお読みいただきたいと思います。
タンパク尿とは
タンパク尿は腎臓に何らかの異常が起きていることを示すSOSのような役割をになう検査異常です。
腎臓という臓器は「必要な物を体に留めて、不要な物をろ過して尿として体の外に出す」臓器です。
腎臓の糸球体(しきゅうたい)というフィルターのような構造がこの役割を担っており、蛋白は私達の体にとって必要な物なため原則外に出る事はありません。
尿中にタンパクが混じっているということは、糸球体をはじめ腎臓に何らかの異常がある可能性があります。
タンパク尿が出る原因
タンパク尿が出る原因のパターンは、大まかに3種類あります。
- 生活習慣病が原因:糖尿病性腎症、高血圧、肥満など
- 免疫や遺伝の病気が原因:IgA腎症(慢性糸球体腎炎)、ネフローゼ症候群、血管炎など
- その他:起立性タンパク尿(腎臓に異常なし)
この3パターンの中でどれに当てはまるかを調べるために、腎臓の特別な採血、尿検査、エコー検査を行ないます。
タンパク尿を放置すると
過去に沖縄で行われた研究で、尿タンパクの検査を行った住民を対象に、17年後にどのくらいの人が透析になったかを調べた研究があります。結果は以下のような結果となりました。
タンパク尿「2+、3+」の人はそうでない住民と比較して、透析が必要になる確率が高いということがわかりました。
そのため、タンパク尿が(2+)、(3+)の場合は、症状がなくても要注意です。
詳しくは日本腎臓学会が発行する「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2018」をご参照ください。
タンパク尿を改善させる治療・方法
1度悪くなった腎臓を再生する方法はありませんが、タンパク尿を改善させることで残っている腎機能を保護することができます。
タンパク尿が出ている原因にもよりますが、食事・運動の治療、薬の治療が大切です。
食事の治療としては、塩分を減らして、定期的に評価をしながら野菜・果物・タンパク質の量を調整することが大切です。(詳しくは別ページ「腎臓病に良い食べ物で腎機能の低下を防ぐための3つの基礎知識」をご参照ください。)
運動の治療としては有酸素運動や筋力を鍛える運動をします。近年誕生した腎臓リハビリテーションと呼ばれる腎臓のための運動療法もあります。
これらは専門の管理栄養士や運動の療法士さんと相談して治療を行うのが望ましいです。
薬の治療は、特に血圧と血糖値の治療が大切です。腎臓を守る作用がある「RAS系阻害薬」、「SGLT-2阻害薬」を組み合わせて治療をすることが望ましいです。
詳しくは日本腎臓学会のガイドラインをご参照ください。
タンパク尿を指摘された時に行うこと
健康診断などで指摘されたら是非、当院にご相談をください。。。と言いたいところなのですが、遠方だったり、多忙で時間がとれない方も多いと思います。
そのため医療機関に受診できない方にはまず以下のような対応をしてみることをオススメしています。
① お近くの薬局などで尿蛋白を調べる試験紙を購入して、自宅で測定してみる。
② その際には、朝一番に尿検査を測定することにして前日の寝る前に尿を完全に出す。
③ それでも尿蛋白が何度も検出される場合は、医療機関を受診する。
健康診断や薬局で購入できる試験紙の検査は、「定性検査」とよばれる尿検査で(-)、(±)、(1+)、(2+)、(3+)という形で結果を出します。
この検査の難点は、タンパク尿を濃度でみているため、水分不足などで尿が濃くなっているときに検査をすると本当は異常じゃないのに異常と検出されることがあります。複数回測定することで精度を上げることができます。
また、一部の人には日中動きまわると尿にタンパクが出てしまう人がいます。
そのため寝る前に完全排尿して、朝一番の尿をとることでリアルな腎臓のSOSである尿蛋白があるかないかを判断することができます。
どうしても周りに腎臓内科の医療機関がなかったり、当院に受診できない方は、医療機関で行う「定量検査」を市販の検査キット(予防医療普及協会の糖尿病リスク検査キットで調べることが可能)が販売されているので一度やってみることもお勧めします。
タンパク尿(2+)以上なら迷わず医療機関へ
尿検査で異常を指摘されたドキッとされた方も多いと思いますが、タンパク尿(2+)以上を指摘されたら医療機関を受診されることをお勧めします。
医療機関では「定量検査」と呼ばれる実際1日あたりタンパク尿が何グラム出ているかを調べる検査を行うことが可能です。
「定量検査」は「定性検査」と比較して、濃度の影響を受けづらく正しい評価が可能です。
この定量検査は内科のクリニックだと行っていないこともあり、受診する診療科は腎臓内科が望ましいです。
ただし、中々地域に腎臓内科のクリニックがないこともあるので、内科のクリニックで「尿タンパクの定量検査」、「腎臓のエコー検査」などをやっている医療機関があればそちらでもよいです。
よくある質問
Q1 タンパク質を一杯食べているから、尿タンパクが出るというのは本当ですか?
基本的には、タンパク質を一杯とっていることと、尿タンパクが出るのは関係ありません。異常のない尿タンパクはないです。
Q2 朝の尿が良いと言われたのですが、
早朝の尿で検査をするとより良いです。具体的には寝る前に尿を全て排尿して、その後寝てもらって、起きた時に尿を検査にまわします。成人よりも思春期の方の検査で朝の尿をとってもらいます。
Q3 子どものタンパク尿はどうすればよいですか?
子供のタンパク尿の半数以上は「起立性蛋白尿」と呼ばれる体動に伴う蛋白尿であり腎臓としての異常はありません。ただし背景に腎疾患が隠れていることもあります。この場合は、早朝の尿で検査をすると良いでしょう。具体的には寝る前に尿を全て排尿して、その後寝てもらって、起きた時に尿を検査にまわします。
Q4 尿タンパクだけでなく尿潜血も指摘されています。
尿潜血・タンパクが両方出ている場合は、沸点を低くして精査をすることを推奨します。
タンパク尿で受診を希望の方へ
いかがでしたでしょうか?
健康診断でタンパク尿を指摘され、腎臓が悪いと言われてドキッとされた方も多いと思います。
腎臓は一度悪くなると回復しにくいため、気になる数値を見つけたら、勇気を出して医療機関を受診することをお勧めします。
赤羽もりクリニックでは、腎臓専門医による診察と、特別な腎臓の血液検査・尿検査・エコー検査などを専門的な検査を行い、あなたの腎機能を多角的に評価します。
また検査結果をもとに薬物療法だけでなく、管理栄養士の食事指導などの生活習慣のアドバイスを行い「これ以上悪化させない」をサポートします。
腎機能に不安を感じたら、まずはご相談ください。
もし当院の診療に興味がある方は以下の当院紹介をご覧くださいね。
診療時間
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:40 | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / |
| 14:00〜16:40 | ○ | / | ○ | / | / | ○ | / |
| 16:00〜18:40 | / | / | / | ○ | / | / | / |
アクセス
最寄り駅:JR赤羽駅東口から徒歩4分
例:大宮駅から約20分、東京駅から約25分、上野駅から約10分、渋谷駅から約20分、宇都宮駅から約70分、前橋駅から約80分