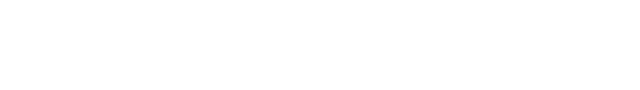糖尿病でもバナナは食べてOK!血糖値を上げにくい食べ方を医師が伝授
こんにちは、赤羽もりクリニックの院長の森 維久郎です。
「バナナって甘いから、糖尿病だと食べちゃダメなのでは…?」と心配される患者さんも多くいらっしゃいます。
確かに糖質を含む果物ですが、食べ方を工夫すれば、糖尿病の方でもバナナを取り入れることが可能です。
今回は、糖尿病の方が安心してバナナを楽しめるよう、血糖値を上げにくい食べ方や注意点について解説します。
(当記事は院長の森医師が監修しております。)
糖尿病でもバナナは食べてOK!その理由とは
バナナの糖質とカロリーは調整可能
バナナ1本(約100g)あたりの糖質は約21g、カロリーは約93kcalです。生のフルーツの中で糖質はやや多めですが、食べる量やタイミング、他の食品との組み合わせを工夫すれば、無理なく食事に取り入れられます。
例えば、「朝食にヨーグルトと一緒に半分だけ食べる」といった工夫は、血糖コントロールにも効果的です。
このあと、具体的なポイントをわかりやすく解説していきます。
GI値と血糖値の上がり方からも安心
GI値(グリセミック・インデックス)とは、食品に含まれる炭水化物が食後の血糖値をどれくらい上昇させるかを示す指標です。具体的には、「ぶどう糖50gを摂取したときの血糖値の上昇を100」とした場合に、その食品がどの程度血糖値を上げるかを数値で比較しています。
GI値が高い食品は血糖値が急激に上がりやすく、低い食品は血糖値の上昇が緩やかになります。つまり、糖質を含む食品であってもGI値が低ければ、血糖値が上がりにくくなります。
例えば、バナナは生のフルーツの中では糖質が多めですが、GI値は中程度です。白ごはんや食パンのようにGI値が高めの主食と比べると、血糖値の上がり方は比較的緩やかになります。
とはいえ、「ごはんは食べちゃダメ?」と思われるかもしれませんが、白ごはんも食べ方次第で問題ありません。肉や魚などのたんぱく質、野菜などの食物繊維と一緒に食べることで、血糖の上昇を緩やかにしてくれます。
大切なのは「何を食べるか」だけでなく、「どう組み合わせて食べるか」です。バナナもごはんも、「食べてはいけないもの」ではなく、工夫しながら取り入れていくことが大切です。
無理のない、続けやすい食習慣を目指していきましょう。
食物繊維で血糖値の上昇を緩やかに
食物繊維は、水に溶ける「水溶性食物繊維」と、水に溶けない「不溶性食物繊維」に分けられます。
いずれも胃や小腸では消化・吸収されず、大腸まで届くという特徴があります。
水溶性食物繊維は、水に溶けてゲル状(ゼリー状)になり、糖の吸収を緩やかにすることで、食後の血糖値の急上昇を抑える働きがあります。
一方、不溶性食物繊維は便のかさを増やし、腸の動きを活発にして排便を促す効果があります。
その他に知っておくべき栄養素
カリウムによる血圧への作用
バナナにはカリウムが豊富に含まれており、このカリウムには体内の余分なナトリウムを排出する働きがあります。ナトリウムが体内に多くなると、塩分濃度を一定に保つために水分をため込みやすくなり、その結果、血圧が上昇しやすくなります。
カリウムを適度に摂ることで、血圧を調整する効果が期待でき、高血圧の予防やむくみの改善にもつながることに。ただし、腎臓の機能が低下している方や、医師からカリウム制限を受けている方はバナナの食べ過ぎに注意が必要です。
カリウムの摂取について制限がある場合は、必ず医師や管理栄養士の指示に従うようにしましょう。
ビタミンB群やマグネシウムも豊富
バナナには、ビタミンB群が豊富に含まれており、糖質・脂質・たんぱく質のエネルギー代謝を助ける働きがあります。また、マグネシウムは骨や歯の形成に関わる栄養素であり、体内の50〜60%は骨に蓄えられているのが特徴です。
さらに、筋肉の働きをサポートしたり、インスリンの作用を助ける役割も担っています。このように、バナナは糖質だけでなく、代謝や骨の健康、血糖コントロールを支える栄養素もバランスよく含んだ、機能的な果物といえるでしょう。
血糖値を上げない!バナナを食べる3つのコツ
糖質を含むバナナも、ちょっとした工夫を加えることで血糖コントロールに役立てることができます。ここでは、糖尿病の方がバナナを安心して楽しむための3つのコツをご紹介します。
たんぱく質・脂質・食物繊維と組み合わせて食べる
バナナには食物繊維も含まれていますが、糖質が多いため、単独で食べると血糖値が上がりやすくなります。そこでおすすめなのが、たんぱく質や脂質・食物繊維を含む食品と組み合わせて食べることです。
無糖ヨーグルトのたんぱく質やナッツの脂質は、消化吸収に時間がかかるため、胃でゆっくりと消化され、糖の吸収速度が緩やかになります。これにより、血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます。
なお、食物繊維については説明の通り、水溶性食物繊維が糖の吸収を緩やかにする働きがあります。バナナを他の食品と組み合わせて食べることで、より効果的に血糖コントロールがしやすくなります。
おすすめの組み合わせ例:冷凍バナナ × 無糖ヨーグルト × きな粉×ナッツ
血糖値を意識しながらも満足感のあるおやつを取り入れたい方におすすめなのが、「冷凍バナナ+無糖ヨーグルト+きな粉+ナッツ」の組み合わせです。
カットしたバナナを冷凍しておくことで甘みが増し、アイスクリームのような食感に。無糖ヨーグルトをかければ、さっぱりとした酸味が加わり、満足感もアップします。
トッピングには、低GI食品であるきな粉(GI値:約30〜40)をプラスしましょう。香ばしさが加わり、味のアクセントになります。さらにナッツを添えることで、良質な脂質と食物繊維も補え、血糖値の急上昇を抑える工夫としても優秀です。
手軽に作れて美味しい、血糖コントロールを意識したおやつとして、ぜひ一度お試しください。
バナナの1日の摂取量は「1本」が目安
バナナは生のフルーツの中では糖質量が多いため、食べすぎると血糖コントロールが難しくなります。1日1本までを目安にしましょう。
食べるタイミングは「朝 or 食後」がおすすめ
バナナは糖質が多いため、空腹時に単独で食べると血糖値が急上昇しやすくなります。そのため、主食の一部として朝食や食後に食べるのがおすすめです。
食べる際には、野菜や卵などの食物繊維・たんぱく質を含む食品と組み合わせることで、糖の吸収が緩やかになり、血糖値のコントロールがしやすくなります。
また、朝食そのものが血糖コントロールにおいて重要な役割を果たしています。朝食を抜いてしまうと、夕食から昼食まで10時間以上の空腹状態が続くことに。
この長い空腹により、体は「飢餓状態」と判断し、インスリンの分泌や働きが鈍くなることで、次の食事である昼食後の血糖値が急激に上昇しやすくなってしまうのです。
さらに、朝食を抜くと、インスリンが分泌されるタイミングを逃してしまうことがあります。本来スムーズに血糖を下げるはずのインスリンの働きが遅れてしまい、血糖値が大きく変動する原因になります。
また、夜に食べるとエネルギーとして使いきれず、脂肪として蓄積されやすくなるため注意が必要です。
完熟バナナと青めのバナナの違いは?
熟したバナナは糖質が分解されて糖分が増えるため、血糖値が上がりやすくなります。一方、両端に緑色がうっすら残る程度のバナナはでんぷんが多く、GI値が熟したバナナよりはやや低くなります。
そのため、血糖値が気になる方は、少し青みが残ったバナナを選ぶのがおすすめです。
さいごに
いかがでしたでしょうか?
今回は、糖尿病の方でも安心してバナナを取り入れるための工夫やポイントについてご紹介しました。バナナは適切に摂れば、血糖値を安定させながら栄養を補える優れた果物です。
糖尿病だからといって、すべての果物を避ける必要はありません。バナナも食べ方を工夫すれば、安心して楽しめる果物の一つです。
食べる量やタイミング、組み合わせを意識して、血糖値と上手につきあっていきましょう。
赤羽もりクリニックでは、医師と管理栄養士が連携し、一人ひとりのライフスタイルや好みに合わせた食事のご提案を行っています。
「果物の摂り方がわからない」「食事の工夫で血糖値を安定させたい」といったお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
最寄り駅:JR赤羽駅東口から徒歩4分 例:大宮駅から約20分、東京駅から約25分、上野駅から約10分、渋谷駅から約20分、宇都宮駅から約70分、前橋駅から約80分診療時間
受付時間
月
火
水
木
金
土
日
9:00〜12:40
○
/
○
○
○
○
/
16:00〜18:40
○
/
○
○
/
/
/
14:00〜16:40
/
/
/
/
/
○
/
アクセス